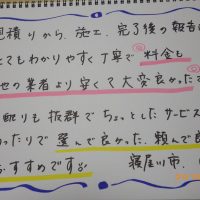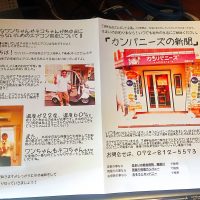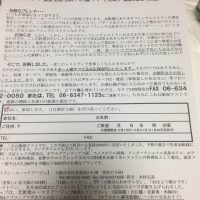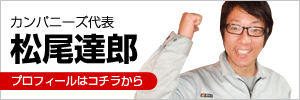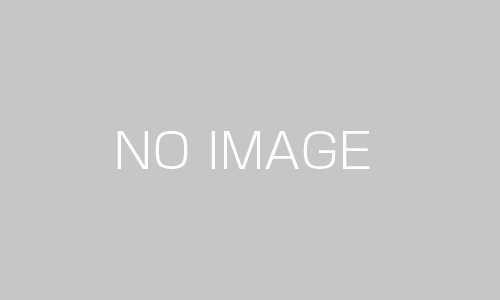昨今、コミュニティーに対する議論が活発にされている。
キュレーションNews Picksでも時代の先頭を走っているクリエイターの方々がトークしている。
企画ユニット「プラネッツ」を主宰し、今年に入りオンラインサロン「planets club]を解説した宇野常寛氏
そして、「コルクラボ」を運営する元講談社のコルク代表の佐渡島庸平氏
仮装ライブ空間「showroom」を立ち上げ、夢を叶えたい演者にコミュニティー・プラットフォームを提供している前田祐二氏
幻冬社で書籍編集者を務める傍ら、1000人規模のオンラインサロン「箕輪編集室」を主宰する箕輪厚介氏だ。
上記のそれぞれの人は、自身が発信した情報からコミュニティーを作っている方々。
箕輪氏曰く、
コミュニティーに関心が集まる理由が3つあると思うと話す。1つ目は、「社会文脈としてみんなが孤独になっている」こと、2つ目は、「オープンすぎるインターネットに疲れて閉じる方向に向かっている」こと、3つ目は「持続的なビジネスをする上で必要」
さらに前田氏は、
コミュニティーは「絆の集合体」と語っています。その空間において1対1の深い心の繋がりをどれだけ新しく創出し、そして、維持できるか。
シンプルですが、この考え方がコミュニティー設計において極めて大切な基本です。集権型ビジネスモデルを志向するこれまでの芸能界においては「幅」重要視されます。演者とファンの絆の深さ以上に、薄くてもその演者のことを認知している人の数が多い事に価値をおく世界です。単純に言い換えれば、演者とファンの「1対N」の関係に置いて、Nの人数が多い程、経済的価値があった。
一方で、コミュニティの考え方は真逆で、幅よりも「深さ」を施工します。たった100人、いや、10人いなくても良い。その10人がどれだけ「深く」そのコミュニティに可処分精神を咲いているか
この部分は、持続的なビジネスをする上でとても重要な話ですね。そしてスモールビジネスの私たちにも勇気を与える話です。
例えば、習い事ビジネスでも以前はどれだけたくさんの生徒さんを抱えるのかがビジネスの肝でしたが、これからはどれだけ「深く」絆を創出するのかが大切な考えになってきます。
たった100人のコミュニティでも「深さ」を追求することによりリピート率も含め、習い事全般にビジネスが波及していく可能性がある。
コミュニケーションディレクター、佐藤尚之氏も参戦
これからの企業に「ファンベース」が不可欠な理由、
従来型のマスマーケティングは、一過性で終わることが多い。これからのマーケティングは、ファンを大切にして、中長期的に売上や価値を高める「ファンベース」の考え方を意識しなければならない。
佐藤尚之氏が伝えているのは、ファンからお金を稼ごうという意味合いではなく、ファンとともにブランド価値を高めて行く考え方なのでファンビジネスやファンマーケティングなどとは異なる目的です。
ただし、これまで論じてきたコミュニティーは全国レベルで作るコミュニティーの場合ですが、コミュニティーに関しては地域密着型も非常にマッチする仕組みではないかと感じます。
例えば読書会のコミュニティもそうですが一つの地域で始まり、それが伝播して新しい拠点が増えていくことが多いです。
例えば大阪の梅田でスタートした読者会が大阪堺市でも波及し全国にも波及することは普通にあります。
私たちは、それを習い事のコミュニティで構築していこうと考えています。ご存知の通り女性は習い事が大好きです。そこで共通の言語を持つ人々のコミュニティであれば必要にされると考えられます。
これはあらゆるビジネスに必要な考えで、売り手と買い手が別れるのではなく、売り手と買い手の線引きがない状態になって行きます。
現に、クラウドファンディングでは買い手が参画者や応援者としてお金を払います。私が入っている会員制の焼肉屋さんは低温調理の焼肉屋で部位により最適の温度を導き出し、最高の状態で肉を食する、をコンセプトにしている焼かない焼肉屋です。
クラウドファンディングの時点で会員制を打ち出し永久会員として登録しました。定員15人ぐらいのお店で300人の会員さんがオープン前に集まっていました。この状態はオープン前から売上が立ち、コンセプトを理解した肉好きのコミュニティが出来上がっています。
飲食店は立ち上げまでの広告費やお客さん作りリピーター作りができずに撤退するお店がほとんどです。しかし、コンセプトがあり独自性と顧客目線のビジョンがあれば資金調達、お客様調達までもが可能になっている時代です。
会社やお店が潰れるのはお金がなくなったからではなく、お客さんがいなくなったから
そうなんです。あらゆる会社はトヨタであろうが町の床屋であろうが、お客さんという応援者がいなくなった時に必要ではなくなるのです。
この頃よく言われているスナック最強論。
シャッター商店街の中でも生き残っているお店がスナック。ママさんと常連のお客さんで成り立っている。決まった食事が出るわけでもなくママ特製のポテサラなどが出てくるだけ。しかし、ママが飲みつぶれても常連のお客さんは怒らない。そこに新規のお客さんが来ても酔いつぶれたママの代わりにお酒を作ってくれたり、ママの良いとこを話してくれたりする。まさにスナックとママを起点にコミュニティ、集まる場所ができている。
この「社会文脈としての孤独」な時代に居場所を作ることがこれからは益々必要にされるのだろうと思います。